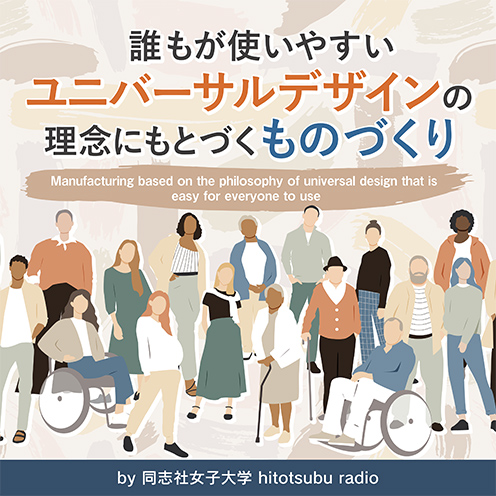#1 実はこれも。身の回りのユニバーサルデザイン【土井 幸輝】
「ユニバーサルデザイン」は、どのような形で日常に用いられているのでしょう?私たちにとって身近なものを例に挙げて、土井先生に教えていただきました。どんな点に特徴があるのか、使いやすいのか一緒に考えてみませんか。
/ 13分58秒
今すぐ聴く
各ポッドキャストで聴く
Transcript
川添 今回は、生活科学部人間生活学科教授で、人間工学、福祉工学がご専門、ユニバーサルデザイン分野で教育、研究活動を行っている土井幸輝先生に、「誰もが使いやすい、ユニバーサルデザインの理念にもとづくものづくり」をテーマにお話を伺います。
全4回にわたって、ここ京都にあります、同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
土井 よろしくお願いします。
川添 先生は人間工学、福祉工学がご専門と、先ほどご紹介をさせていただいたんですけれども、私たちリスナーからすると、少しイメージがしづらいところもあるので、具体的にどのような分野なのかをまずはご紹介をいただきたいと思っております。
土井 はい。人間工学、福祉工学、皆さんお聞きになったことはないと思います。私は、福祉、教育、生活の各分野で利用者の皆さんのニーズに沿ったさまざまな製品の開発、または評価に携わっています。人間工学とは、人々が生活しやすい環境を実現し、安全で使いやすい道具や機械をつくるために、学術的に使いやすさを評価してデザインしていく学術研究領域の一つです。
川添 はい。
土井 福祉工学は、高齢者の方や障がいのある方の日常生活を支える器具、機械を開発、改良する学術研究領域になります。それらを基盤として、さまざまな人々が生活しやすい社会を実現したいと、私たちは考えています。さまざまな製品の開発、評価研究に取り組んでいるわけです。
川添 はい。
土井 川添さん、テーマである「誰もが使いやすい、ユニバーサルデザインの理念にもとづくものづくり」の中のキーワードの一つである、ユニバーサルデザインって聞いたことありますか?
川添 そうですね、最近よく聞くようになりました。例えばですけれど、私の身近なところでは仕事でWordを使ってテキストを書くためにフォントを選ぶとき、UD(=ユニバーサルデザイン)フォントというのがあるのをよく見るようになりました。それを選んで使うということは、一番身近なところではあるかなと思ってるんですけど。ただ、きちんと説明できるかと言われたら、正直なところ、ちょっとまだ理解が及んでない部分があるんじゃないかなと思っています。
土井 そうですね。ユニバーサルデザインフォントはお子さんたち、今の小学生とか中学生、高校生もそうですけれど、普段使ってる教科書に、多様な人々が読みやすいフォントとして一般に普及してきています。
そういったところでユニバーサルデザインというのを聞いたことあると思うのですが、少しずつ普及してきています。
川添 はい。
土井 普遍性を考慮した製品の設計とか、デザインを実現するための理念の一つとして、ユニバーサルデザインというのを位置づけることができます。
川添 そうなんですね。
土井 ユニバーサルデザインは特別な改良、特殊な設計をしなくても、年齢の高低、障がいの有無に関わらず、より多くの人々が可能な限り最大限まで利用できるように配慮された製品、環境のデザインのことなんです。つまり、多様な人々の利用を想定したものづくりやサービスの普及をめざした理念の一つが、ユニバーサルデザインであるといえます。
川添 多様な人々の利用を想定している。ものづくりとかサービスの普及をめざした理念の一つということなんですね。
土井 はい。
川添 そういったユニバーサルデザインというのは、私たちの日常生活の中で、見つけることって簡単にできるものなんでしょうか?
土井 そうですね、我々も意識して、「ユニバーサルデザインの製品はどこにあるんだ」というふうに生活しているわけではないんですが、実際には私たちの生活の隅々に溶け込んでいるというふうには言えます。
川添 そうなんですね。
土井 例を挙げてみますと、シャンプーの容器の側面、あるいは天面のポンプの上に付けられた刻み状の突起は一例と言えるでしょう。あるいはコンディショナーの容器は、容器の側面、天面ポンプに突起を付けていないデザインとなっています。
これら二つを触り比べてみると、突起のついているシャンプー、付いていないコンディショナーは触っただけで区別することができます。そのため、視覚に障がいのある利用者だけでなく、私たちが洗髪中で目を閉じたままでも使い勝手が良いので、多様な人たち、視覚障がい者の方だけではなくて、晴眼者の我々にも有用なデザインと言えます。
もう一つ事例を挙げてみましょう。スペースを工夫したユニバーサルデザインの例として、駅の改札が挙げられます。川添さんも日々電車を使って通勤されていますか?
川添 最近は少ないですけども、利用します。
土井 本学の学生も電車で駅を利用して通学していますが、最近の駅の多くには通り抜ける幅の広い改札が1ヶ所は配置されています。
車椅子の利用者、あるいは松葉杖の利用者、歩行補助具を使う高齢者はもちろん、大きな荷物を抱えた人、ベビーカーを押している人など、誰でも改札を利用しやすいデザインになっています。こうした改札、川添さん見たことありますか?
川添 ありますし、私の子どもが小さかったとき、ベビーカーを使ってたときは、私は1人用のベビーカーでしたけれど、それでも普通サイズの幅の改札を通れるか通れないかと、いつも見極めながら通ってたりとか。双子用のベビーカーなんかは横に広い、縦に長いバージョンもありますけど、子育て界隈ではよく話題になりました。
土井 そうですね。こうしたちょっとした工夫で、たくさんの利用者が利用しやすくなるというようなことで、一つ例としてこの駅の改札も挙げさせていただきましたが、もう一つ挙げてみたいと思います。
川添 はい、お願いします。
土井 学食など、学生さんも普段利用するところにも設置されているものの一つとして、センサー式の蛇口があります。これもユニバーサルデザインの例として挙げられます。手を蛇口付近に近づけると赤外線センサーが反応して自動的に水が出る仕組みです。障がいのある方、あるいは握力の弱い子どもたちや高齢者など、栓をひねることが難しい人の利便性を高めるというふうに言えます。公共のトイレなど不特定多数の人が利用する箇所で重宝されています。蛇口に触ることなく水を止めることができますよね。
川添 そうですね。
土井 感染対策としても効果的です。その他にもたくさんありますが、このあたりにしておきたいと思います。
川添 ありがとうございます。このセンサー式の蛇口が、ユニバーサルデザインの例として挙げられるものだったんだというのを今、ハッと気付かされたような部分がありました。結構、身近なところにはユニバーサルデザインというのは普及しているんですね。
土井 そうですね。
川添 それをお伺いして、一方で、「そういえばバリアフリーという言葉もあったな」と、チラッとよぎったんですけれども、このバリアフリーとは異なるんですか。
土井 はい、大切な視点ですね。バリアフリーについても、ユニバーサルデザインと並んで大事な理念の一つということになりますが、バリアフリーは障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁、バリアとなるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語として登場し、段差等の物理的障壁を除去することを意味していました。しかし今ではより広く、障がいのある方々や、高齢者の皆さんの社会参加を困難にしている「社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去」という意味で用いられるようになってきています。
川添 はい。
土井 ここで川添さんに。具体例にですが、視覚障がい者のための放送サービスとして、番組音声だけでは伝わらない情報を、副音声で補完する解説放送というのがありますが、これはご存知ですか。
川添 はい、聞いたことがあります。
土井 皆さんもNHKなどでこうした解説放送をご覧になられたことがあるかもしれませんが、こうしたものも一つ、バリアフリーとして挙げられます。また視覚障がい者が安心安全に移動できるように、黄色の誘導ブロックが駅や道路に設置されています。これは、点字ブロックというふうに言われることがありますね。
これらもバリアフリーの一つというふうに位置づけられます。あらゆる場面でこれからバリアフリーが実現されて、加えてユニバーサルデザインの理念にもとづいて、施設、設備、製品、またサービスが提供されるようになると、多様な人々が生活しやすい社会になっていくと考えられますので、バリアフリーも極めて大切な理念の一つです。
川添 そうなんですね。ユニバーサルデザインもバリアフリーも、いろんな人、多様な人々が円滑に社会参加できて、心地よく生活できるようにするためには、本当に欠かせない理念ということですね。
土井 そうですね。まさにおっしゃる通りです。私もユニバーサルデザインやバリアフリーの理念にもとづいた製品開発に携わってきましたので、皆さんにもこのラジオを通して少しでもこの分野に関心を持っていただければというふうに思ってます。
川添 先生は誰もが使いやすいユニバーサルデザインのものづくりとか、バリアフリーの考え方に基づいた福祉用具の改良などにも携わってこられていますので、次回からは先生が携わってこられたことについて、詳しくお話をお伺いできたらと思っております。また引き続きよろしくお願いいたします。
土井 よろしくお願いします。
川添 本日はありがとうございました。
土井 ありがとうございました。